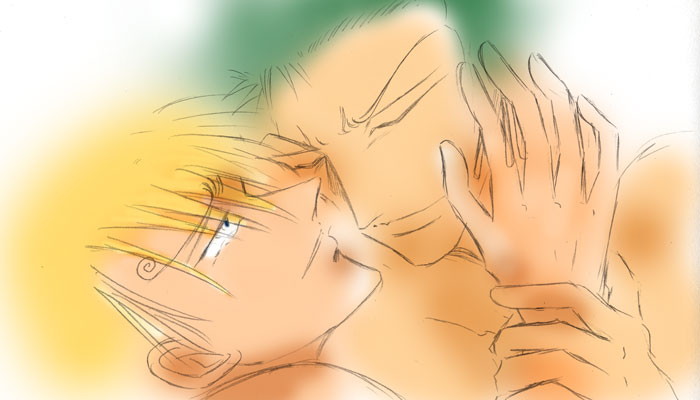BEFORE 静かな夜だった。 寄り添い、肌を合わせているだけで、満たされる。 部屋の暖房は消えているのに、少しも寒くはなかった。 ソファに並んで座り、ゾロの肩に体を預け、サンジはずっと立ち昇るタバコの煙を見つめていた。 時々、ゾロがグラスを口元に運ぶ。 すると、静けさを、氷が揺れる音がやんわりと裂いた。 サンジが、囁くように言う。 「ルフィのヤツも…ずっと待ってたんだな…ナミさんが、自分を追いかけてきてくれるのを…。」 「…そうだな…よくよく考えりゃそういう事だ。ナミにだけ送ってくるメールの意味は。 “今、オレはここにいる。だから、来い。”…ったく…素直に言やあいいんだよ。“来い“ってよ。」 「言えなかったんだろ?ナミさんだって、好きな仕事に一生懸命だったんだ。それを捨てて、 “オレのワガママ旅に付き合え”なんて、いくらルフィでも言えねぇよ。」 「…そうだな。…しかし何だ?お前、随分ルフィを知った風な口利くな。」 「ん?…ああ…そういやそうだな…はは…なんだか、もうずっと前から、アイツを知ってたような気がする。 変だよな。今日、初めて会ったのに。」 「…なんか知らねぇが…今、ちょっとムカついた。」 「…あ〜ルフィが言ってたけどな。お前、結構ヤキモチ焼き?」 「…今頃気づくな、アホ。」 ゾロが笑う。 サンジも笑う。 「ゾロ。」 「ん?」 「お前は…ちゃんと言ってくれよ?」 「………。」 「オレに来て欲しい時は、必ず言ってくれ。そしたらオレは、這ってでもそこへ行くから。」 「………。」 「必ず行くから。」 「ああ。」 ああ、やっぱりオレはコイツが好きだ。 互いに、同時に、そう思う。 ゾロの両手がサンジの頬を包む。 包んで、引き寄せ、また自分も顔を寄せて、唇を奪った。 繰り返す 繰り返す 何度も何度も キスして、抱きしめて、またキスして 「…いいか…?」 ゾロが囁く。 サンジの他に、誰も聞くものはいないのに、まるで潜めるような声で。 「…いいか?」 また、ゾロは尋ねる。 サンジは黙って、だが大きくうなずいた。 瞬間、ゾロの腕が荒々しくサンジを抱きしめる。 「…もう…何にも邪魔されねぇ…!お前自身にもだ。」 「…好きだよ…ゾロ。」 「ああ、よく知ってる。」 「好きだ。」 「ああ、オレもだ。」 「好きだ、ゾロ。」 「ああ。」 「好きだ、好きだ。」 「ああ。…ああ!」 「愛してる…。」 深いキスが答える。 そして、言葉でも。 「愛してる、サンジ。」 ゾロの手が、不器用にシャツのボタンを外していく。 上手く外せず、下の方の幾つかは、短気に引き裂いてしまった。 「バカ野郎!お前!高いんだぞ、このシャツ!」 「うるせぇな!焦れってぇんだよ!!ずっと…お前のことばっか考えて…今、やっと、こうしてるんだ!! そんなにちんたらヤれるほど、今のオレにゆとりはねぇ!!」 「ここまで引っ張ったんだから、ムードとか少しは考えるってコトはしねぇのか!?」 「んなモン期待すんなぁ!!」 少し、後悔? いいや 「…わかった…なァ…じゃあ…自分で…脱ぐから…。」 自分で? 「サンジ…。」 「………。」 「…おい…無理すんな…。」 サンジが首を振る。 「じゃあ、灯り消すぞ。」 「いい、消すな。」 「サンジ。」 「…見てくれ…。」 あの時は、ゾロが無理矢理脱がして見た。 だが今、サンジは、ためらうことなく全ての衣服を脱ぎ捨てた。 自分から、動かない足を器用に手で動かしながら。 白い、2本の足。 きっと、綺麗な足だったのだろうに。 太腿の中央から、足首にいたるまでの大きなケロイド。 どんな状態で、熱した油がこの足にかかったのか想像がつかない。 一番酷いのは、右足の膝から踝の辺りまでの傷だった。 肉がえぐれ、皮膚が引きつって、直接骨が浮き出ている。 油で、焼き崩されてしまったのだ。 足の骨格を覆う肉が、一切無い。 当然、感覚をつかさどる神経も、全て奪われてしまっている。 「………。」 少し、困ったようなサンジの顔。 ゾロの表情が、よほど痛々しかったのだろう。 それに気づき、ゾロは苦笑いを浮かべた。 「2度目でも…気持ち悪いだろ…?」 「…ああ、ちょっとな。」 「…正直さって残酷…。」 「…ありがとう…。」 ゾロが言った。 素直な感謝の言葉。 全てを自ら晒してくれた、サンジへの。 その足へ、ゾロは口付ける。 最も悲惨な右足へ、ためらうことなく、ゾロは舌を這わせた。 「…っ…あっ…!」 その反応に、ゾロも驚いたが、サンジ自身も驚いた。 「…感じる…のか…?」 「……感じる…嘘だ…だって…今まで、何したって感覚なんか無かったのに…。」 もう一度、と、ゾロは深い傷跡の部分にキスをする。 「…っ…。」 「…感じてんな…気のせいじゃねぇ。テメェ、ちゃんと感じてんじゃねぇか。」 「…う…うん…なんだよ…テメ…そのガキみてぇにウレシそうなツラ…。」 「嬉しい。マジで嬉しいんだよ。」 「………。」 ああ、もう 「わかった…。」 小さく、サンジは笑った。 目に、薄く涙が光る。 「お前の好きにしていいよ…。」 「ああ、だけどな。」 「?」 「…ちゃんと…お前も、ヨクしてやっかんな?」 「…アホ…。」 サンジの体の麻痺した部分は、正確には大腿部から下の範囲だ。 太腿の上をゾロが触れれば、サンジは魚の様に跳ね、背中を反らす。 感覚のないはずの足も、ゾロの熱い指を、濡れた舌を、感じてかすかに震えていた。 自分の愛撫だけを、受け止め、反応する。 そう思うだけで、ゾロの血が熱くなった。 「…あ…ゾロ…なァ…そんなに…足ばっか…。」 動かない両足を腕に抱え込んで、ずっと愛撫とキスを繰り返している。 自分ゆえに感覚を取り戻す足を、ゾロは心底喜んでいた。 「…感じるだろ?感じろよ…もっと…。もしかしたら、続けてるうちに歩けるようになっちまうかもな。」 「んなワケあるか…。」 「試してみなきゃ、わからねぇだろ?」 「…バカ…。」 小さく声を挙げながら、サンジは半身をわずかに起こして、ゾロの髪に指を差し入れた。 「…な…ゾロ…。」 「あぁ?」 「………。」 「何だ?イヤか?」 「…違う…そうじゃね…そうじゃなくて…。」 「?」 「…もっと…他のトコも…。」 サンジの顔が、真っ赤になる。 「…他のトコも…触って…。」 その一言に、ゾロの顔も赤く染まった。 「…ああ…。」 「………。」 「…例えば、こっちとか?」 「!!…ん…んあっ…!!あ…!」 いきなりそっちに来るか? 声にならなかった。 堅くなり、震えるサンジのそれを、ゾロの手が優しく愛撫する。 足を抱えていた手がそのまま後ろに回り、指がそこに触れた。 「…あ…あああ…っ!!」 麻痺した足でさえ、あれだけ感じた。 感覚のある肌に、一番敏感な部分に、触れればもっと感じるのは当たり前のことだ。 あまりの自分の声に、サンジは我に返って口を覆い隠す。 羞恥が一気に襲い掛かり、体をひねっていやいやと首を振った。 「かまわねぇ。誰も聞いてるヤツなんざいねぇだろ?」 手を握り、指に口付け 「恥ずかしいなら、オレが塞いでやる。」 唇を吸い、舌を絡める。 首筋を、胸を、肩を、何度も何度もキスし、肌を探ってはまた抱きしめる。 「…ゾロ…ゾロ…っ!」 ヒクヒクと震え、サンジがゾロにすがりつく。 手が、震え、ためらいながらゾロの手を握り、おずおずと半身へといざなう。 「イキてぇか…?」 「…ん…んん…っ。」 小さくうなずく金の髪。 「いいぞ…ちょっと待て。」 ゾロは、手をついて半身を起こし、そのまま下へ移動した。 そして、抗う術の無い足を開いて、その間へ顔を埋める。 「あ!!ゾロ…やっ!!」 「こっちの方が、気持ちイイだろ?」 「…あ…ダメだって…手でいい…から…!!」 「オレがこうしてぇんだ。いいから感じろ。感じてイキたい時にイっていい。全部…こぼさないでやる。」 「あ…ああ…!」 柔らかな袋を揉みしだきながら、舌で、堅くなった血管を辿る。 前後する舌の動きが、サンジの視界を真紅に染めた。 ゾロの舌にからめとられたものがたまらなく熱く、耐え切れずに、ゾロが煽るままに吐き出した。 「…あ…は…っ…。」 小刻みに震える体。 無意識に、サンジはゾロを探した。 自分を抱きしめているはずなのに、その顔がどこにあるのかさえわからない。 舌の、濡れる音がした。 たった今、サンジが吐き出し、わずかに指にこぼれたものを、ゾロは甘い蜜を舐め取るかのように舌で掬う。 「…バカ…汚ねぇ…。」 「汚いワケあるか。…うつ伏せにするぞ…いいか?」 「…ん…。」 「辛かったら、すぐに言えよ。」 サンジはうなずく。 足を抱え、ゾロの手は容易く、サンジの体をソファの上にうつ伏せにさせる。 そして、白く締まった果実の割れ目に、舌を挿し入れた。 「あ…!ああ…!!」 一度達していた体は、信じられないほどに敏感になっていた。 舌で濡らされ、指で探られて、その指先が、最も感じる部分に触れた時、まるで電流が走るような快感に襲われた。 「ひっ!あぁっ!!ああああああっ!!」 「ここか。」 「やっ!!やめ…!!」 「やめねぇ。」 背中から抱きしめ、それを刺激するのをゾロは止めようとしない。 腕の中で跳ね回る上半身を、ゾロは感動の思いで見つめた。 サンジの目から、ぽろぽろと涙がこぼれる。 悲しみの涙も、怒りの涙も、喜びの涙も、快楽の涙も どれもなんて綺麗なんだろう。 ゾロのそれも、もうこれ以上耐えられないほどに怒張していた。 猛り狂うそれを、舌で濡らしたその秘所へ背中から押し当てた時、サンジがびくりと震えた。 「…ゾ…ロ…。」 「…いいな…?」 「…う…。」 「……ダメだ…イヤだって言われても…もう無理だ…。」 「…言うかよ…!」 本来、それを受け入れる為のものではない。 それでも、そこに快感の部位があるのなら、それは許される行為だ。 「力抜いて…息、吐け…ゆっくり…。」 ハアハアと、小刻みに刻まれていたサンジの呼吸が、乱れながらもゆっくりになる。 わずかに弛緩するタイミングに合わせて、ゾロは体を押し進めた。 「あ!ああ―――!!」 ゆっくりと、男のものが押し入ってくる異物感。 吐きそうになる不快感が、体の中を逆流してくる。 「…もう少し…も、ちっと…頼む…全部入れてぇ…!」 「…や…や…もう…。」 ぶるぶる震える白い肌。 抱きしめ、貫きながら、何度も背中に口付けた。 「…あ…ああ…ゾロ…!」 「…サンジ…!」 ためらいはあった。 それでも 「…遠慮…すんな…よ…っ…イヤ…ったって…本音なワケ…あるか…っ。」 「…サンジ…。」 「…それとも…アレか…?足…動かせねぇヤツとのセックスじゃしらけんのか…?」 「…んなワケねぇだろ…っ!!」 ゾロは深く息をついた。 「…あ!ああ―――あああ―――!!」 ずぶり と、部屋中に響く音だった。 ゾロのそれが根元まで、サンジの奥へと突き刺さった。 「ああ…!あ…!デケ…ェ…腹ン中…いっぱい…。」 「…苦しいか…?」 「…ン…んん…っ。」 サンジが首を横に振る。 耐えているのが、痛いほどわかる。 だが欲しい。 この快楽の果てが。 「あっ…!あっ!あっ…!…!」 もう、サンジを労わるゆとりなどゾロには無い。 愛しくて、ただただ、愛しくて。 身を繋げた悦びが大きくて。 傍らに、あるべきものを手に入れた喜びが大きくて 想いを、ひとつにできた嬉しさが、たまらなく溢れて。 「ああ…ゾロ!!ゾロ…!」 「このままイクぞ…!頼む…全部受け止めてくれ…オレの全部…!!」 サンジがうなずく。 何度も。 激しく体を揺らしながら、ゾロは咄嗟にサンジの体を入れ替えて、正面から抱き合った。 固く、互いの背中に手を回し、更なる深みを求めて―――。 「…サンジ…っ…!」 名を呼び、深く体を押し当てて、サンジの中へゾロは愛しさの全てを吐き出し、注ぎ込んだ。 果て、力尽き、サンジの上に全身を預けたゾロの背中を、サンジの手が優しく包んだ。 「…ゾロ…。」 「………。」 はあはあ と、ゾロの荒い息だけが答える。 サンジが差し伸べた手を、しっかりと握ることでしか、呼びかけに応えられなかった。 目がかすむ。 「…ゾロ…?」 「………。」 「………。」 サンジが、涙を滲ませて小さく笑った。 そして 「…何泣いてンだよ…バーカ…。」 言いながら、自分の頬にも、熱いものが流れていくのをサンジは感じていた。NEXT (2007/6/22) BEFORE にじはなないろTOP NOVELS-TOP TOP